寺ネット・サンガ 過去のイベント一覧
-

寺ネット・サンガ「坊コン」「第6回お坊さんあるある!」
坊コン
2014-10-01
2014年9月29日(月)、寺ネット・サンガ主催の「坊コン」「第6回お坊さんあるある!」が開催されました。思わずお坊さんたちが「あるある!」と頷いてしまうことをテーマに、お坊さんたちの日常に迫る大好評シリーズです。 第6回目のお坊さんは、港区曹洞宗正山寺ご住職、前田宥全さんです。 前田さんの「お坊さんあるあるー!」という元気の良い掛け声で、プチ法話が始まりました。 ○お坊さんあるある! その1「女子高生が・・・」 お盆の頃、前田さんがお盆のお経参りをしていた際、二人の女子高生に二度見されたそうです。そして聞こえてきた声が、「まじ? またいた〜!」。 どうやらお盆期間中、女子高生たちはお坊さんたちを何人か見ていて、「またいた!」と話題になってしまったようです。 ○お坊さんあるある! その2「地下鉄で・・・」 知らない男性に声を掛けられた前田さん。 「お前は地獄に堕ちている」と言われたそうです。 そこで前田さんは「私が地獄に堕ちているって本当でしょうか?」ときいてみたところ、男性は「そうだ」と言います。 すかさず「地獄に堕ちている私と話しているあなたは、今どこにいるのですか?」と返したところ、男性は次の駅で下車していったそうです。 禅僧らしい受け答えに「坊コン」に参加していたお坊さんたちも頷いていました。 お坊さんならではの「あるある!」です。
-

仏教ひとまわりツアー 各宗派本山めぐり「増上寺」
仏教ひとまわりツアー
2014-09-01
2014年8月30日(土)、寺ネット・サンガ主催「仏教ひとまわりツアー」が開催されました。 各宗派の大本山をめぐりながら、「修行僧の毎日」に焦点をあてた「仏教ひとまわりツアー」。第3回目のお寺は、東京タワーの近く、徳川家の菩提寺としても知られる浄土宗大本山「増上寺」です。 当日は40名以上の参加者が集まり、賑やかなツアーとなりました。 増上寺のお坊さんから、境内の案内を兼ねて「修行僧の毎日」についてお話を伺いました。 ○浄土宗とは 鎌倉時代、政権争いの他、飢饉や疫病などの天災によって、人々は不安の中暮らしていました。僧侶たちは権力者と結びつき、貧しい庶民は救われることなく、すがるものもありませんでした。 比叡山では「智恵第一の法然房」と称されるほど、勉強熱心であった法然上人は、皆が平等に救われる道を求めます。法然上人は『一切経』の中から、阿弥陀様の御本願四十八願のうち、第十八番目にすべての人々が平等に救われる道を見いだしました。 法然上人のお言葉に、「智者(ちしゃ)のふるまいをせずしてただ一向に念仏すべし」とあるそうです。自身の至らなさを自覚(愚者の自覚)し、「こんな私ですが、どうぞお救い下さい」とお念仏を一心にお称えして阿弥陀様に救いとって頂き、西方極楽浄土に生まれることを願います。 浄土宗のお坊さんの修行の基本は、一心に「南無阿弥陀仏」とお称えすることだそうです。 お念仏の「南無」の部分は「帰依します」という意味で、お坊さんたちは節をつけて、ひたすらお称えします。 本日も移動中の廊下では、修行しているお坊さんのお念仏の声が、絶え間なく聞こえていました。
-

寺ネット・サンガ「坊コン」「第5回お坊さんあるある!」
坊コン
2014-07-30
2014年7月28日(月)、寺ネット・サンガ「坊コン」が開催されました。「お坊さんあるある!第5回目」は、大阪にある真言宗の興徳寺のご住職、青木隆興さんのお話です。 前日、青木さんは傾聴ボランティアのため飛行機で大阪~宮城を日帰りで往復、28日は大阪で月参りの後、3時新大阪発の新幹線に乗って東京の「坊コン」会場に到着したそうです。 多忙なスケジュールをこなす青木さん。普段はどんな日常生活を送っているのでしょう。 青木さんのお寺では年に三回の大きな行事の他に、毎月全部の檀家さんの家でおつとめをする「月参り」があるそうです。 関東では馴染みの薄い「月参り」について、お話を伺いました。 ○月参り(つきまいり) 月命日に毎月お坊さんがお宅にお参りすることを「月参り」と言います。例えば28日が命日の場合、毎月28日に檀家さんのお宅にお坊さんがお参りに伺います。 関西では月参りが盛んで、青木さんは毎日数件のお檀家さんを訪問するそうです。 毎月決まった日にお参りに伺うので、月参りの日は檀家さんも仕事を休みにするなど調整しているケースもあるそうです。中にはお経を読んでいる最中にペットの犬がずっと吠えるので、月参りの日は犬のトリミングの日と決めている檀家さんもいらっしゃるとのこと。 「月参り」の馴染みのない地域では、興味深いお話です。 ○校区の中に約五十ヶ寺ある寺町で 大阪の興徳寺は、寺町にあります。小学校の校区内だけでも約五十ヶ寺もあるそうです。 そのため、青木さんが自転車に乗って移動していると、「ご苦労さん」と気軽に声をかけられることもしばしば。 優しい言葉もあれば、厳しい言葉をかけられることもあります。 青木さんが自転車で去る時に、生活困窮者から「神も仏もあるかい!」と言われたというエピソードもうかがいました。 東京よりも人々が気軽に声を掛け合う環境が大阪にはある、と言います。 ○子どもたちからの質問 小学校の校区の中にあるお寺ということで、職業を知るために、子どもたちが興徳寺へ訪れることがあります。その時、子どもたちから「なぜお賽銭をするのか?」という質問が出たそうです。 お賽銭は「お布施」の一種ですが、現代のお布施は「お金で払うもの」という感覚が強くなっています。 自分の大切なものを捧げて、仏さまのお力を頂くというのが本来の「お布施」の意味。 お坊さんは袈裟をまとっていますが、古くは「糞掃衣(ふんぞえ)」といって、汚くなったボロ切れを人々に施してもらって、つぎはぎにして作ったのが始まりと言います。そこで「布」を「施す」と書いて「布施」というそうです。 「お金がないとお布施ができないのか?」という問題について、青木さんからお話がありました。
-

仏教ひとまわりツアー 各宗派本山めぐり「川崎大師」
仏教ひとまわりツアー
2014-07-01
2014年6月28日(土)梅雨空の中、寺ネット・サンガ主催「仏教ひとまわりツアー」が開催されました。 各宗派の大本山をめぐりながら、「修行僧の毎日」に焦点をあてたツアーです。 第2回目は、川崎の真言宗大本山「川崎大師平間寺」です。 真言宗智山派大本山「金剛山金乗院平間寺」は、広く「川崎大師」の名称で親しまれているお寺です。 お正月には約300万人の人が参拝に訪れるという「川崎大師」。 お護摩修行には、ツアー参加者の他にもたくさんの方々が参拝に訪れていました。 お護摩の修行時間は、川崎大師のホームページでご確認頂けます。 ○お護摩の修行 護摩壇の周囲に、香華や五穀、お供物をお供えし、導師が中央の炉の中に護摩木(ごまぎ)を焚いて、ご本尊・厄除弘法大師さまのご供養にはじまる秘法です。 燃え上がる炎に不動明王の剣を象ったお護摩札をかざし、煩悩を焼き、浄化することで家内安全、災厄消除、所願成就を祈願します。 その際、お大師さまのご宝号である「南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)」とお唱えします。 「仏教ひとまわりツアー」参加者たちは、迫力あるお護摩の修行に圧倒されながら、ご本尊の弘法大師空海上人の御尊像に手を合わせました。
-

「坊コン」「第4回お坊さんあるある!」
坊コン
2014-05-10
2014年5月8日(木)、寺ネット・サンガ「坊コン」が開催されました。 「お坊さんあるある!」では、お坊さんたちが思わず「あるある!」と頷いてしまうエピソードを伺っています。 今回お話いただいたのは、千葉県流山市にある真言宗豊山派、円東寺のご住職の増田俊康さんです。 増田さんはマジックやジャグリング、バルーンアートなど大道芸の特技を活かし、近隣の老人ホームや幼稚園、各種イベントで活動なさっています。今回のプチ法話では、手品を交えながら楽しくお話いただきました。 ○心の中をうつしだす不思議なファイル 増田さんが一冊のファイルを取り出しました。「心の中をうつしだす不思議なファイル」なのだそうです。 ペラペラとページをめくると、ため息をついたり、泣いたり怒ったりしている人の表情が描かれています。不平不満だらけの世界です。 真言宗のお経の中の『般若理趣経』(はんにゃりしゅきょう)には、「如蓮體本染 不爲垢所染 」(じょうれんていほんぜん ふいこうそうせん)とあります。蓮は泥の中に身をおいているのに、咲いた花に泥が混じることがないことを示しています。 悪いものに染まらず、良いものを選び取って美しく咲く蓮の花は、仏さまの象徴でもあります。 私たちも、泥のような世界にあっても悪いものに染まらず、まわりの人の心をやすらかにする蓮の花のような存在を目指すことで、仏さまの世界に近づくことができます。 増田さんが蓮の花びらをかたどったピンク色の散華(さんげ)を取り出しました。 「これを心の中をうつしだす不思議なファイルに入れると……」とファイルに散華をはさみ、再びページをめくります。すると、どうでしょう。 先ほどの泣いたり怒ったりしている絵は、きれいな蓮の花がひらく絵に変わっています。散華の花びらによって「心の中をうつしだすファイル」にやすらかな世界が再現され、大きな拍手が起りました。 ○お坊さんって本当に悟りをひらいているの? 「本当に法力を持っているの?」と子どもたちに質問されて、「超能力ならあるよ」と手品を披露して喜ばせる増田さん。 大人たちも、増田さんの人柄に心を開いて率直な質問をなさるそうです。 「実際のところ悟りってひらいてるの?」「悟りの方法ってどこかに書いてあるんじゃないの? 内緒にしないで教えてよ」。 増田さんは、「空海上人が本に書いてらっしゃいます」と答えるそうです。 「即身成仏」、すなわち悟りを得て仏になる方法を、空海上人は『即身成仏義』の中で記されています。増田さんがわかりやすく説明してくださいました。 「重重帝網(じゅうじゅうたいもう)なるを即身と名づく」という言葉があります。「帝網(たいもう)」とは帝釈天さまの「網(あみ)」の意です。帝釈天さまは宮殿のようなお住まいにいらっしゃって、内も外もイルミネーションのようにキラキラ光輝く網があります。これらのキラキラしている網が、「重重」と重なっている様子をイメージしてください。 これが世の中であり、キラキラ輝いている世の中であるということに気がつく事が「即身成仏」ということです。
-

仏教ひとまわりツアー 第5段 各宗派本山めぐり
仏教ひとまわりツアー
2014-04-21
2014年4月19日(土)、寺ネット・サンガ「仏教ひとまわりツアー」が開催されました。 各宗派の大本山をめぐりながら、「修行僧の毎日」に焦点をあてたツアーです。 第1回目は、大田区池上の日蓮宗大本山「池上本門寺」です。 ○池上本門寺とは 今から約730年前の弘安5年(1282)9月、身延山で体調を崩された日蓮聖人が、病気療養のために常陸の国へ向かう道中、郷主であった池上宗仲公のお屋敷にお寄りになりました。 同年10月13日辰の刻、日蓮聖人は61歳で御入滅なさいました。 池上宗仲公は『法華経』の全文字数69384文字に合わせて、約七万坪の土地を寄進し、「池上本門寺」の礎が築かれます。以来「日蓮聖人ご入滅の霊場」として、730年の歴史を守り続けています。 大堂にて御開帳と御祈願を受けました。 大堂は祖師堂とも呼ばれ、日蓮聖人の御尊像が奉安されています。 日蓮聖人七回忌の際にお弟子さんたちによって建立され、日蓮聖人の生前のお姿に近いと伝わっています。 御尊像のお手に持っている払子(ほっす)は黒い色をしています。 日蓮聖人は大変お母様思いで、お母様の髪の毛を生前は常に身につけていたそうです。御入滅の直前、お母様の髪の毛と一緒に荼毘にふすようにと御遺言があったそうですが、あまりに忍びないということで、払子にして御尊像にお持たせたそうです。「孝道示現のご尊像」と呼ばれる由来でもあります。 御尊像の御衣は年に2回、春の千部会(せんぶえ)と秋のお会式(おえしき)の際にお召し替えします。 日蓮聖人御入滅の日に合わせて行なわれるお会式には、全国から約3万人もの人が参詣します。
-

寺ネット・サンガ「坊コン」「お坊さんあるある!」
坊コン
2014-04-07
2014年3月31日(月)、寺ネット・サンガ「坊コン」が行なわれました。 お坊さんたちが、思わず「あるある!」と頷いてしまうようなお話をお聞きしながら、お坊さんたちの日常を知るシリーズです。 今回「お坊さんあるある!」をお話いただいたのは、大田区池上、永寿院の吉田尚英住職です。 ○「お坊さんが思わず合掌してしまった瞬間とは?」 吉田さんが思わず合掌してしまった瞬間を、9つの項目にまとめてお話いただきました。各項目にまつわるエピソードや、意外な出来事を語ってくださいました。 1、お布施を受け取るとき 2、偉い人に挨拶するとき 3、食事をするとき 4、願い事をするとき 5、子は親の鏡 6、神社や教会で 7、逃げたいとき 8、被災地で 9、相手の仏が見えたとき 5の「子は親の鏡」では、こんなエピソードがあったそうです。 吉田さんがお子さんが小さいころお堂の前でお参りした時のこと。片手はお子さんと手をつないでいたため、片手で合掌のような形をとることもありました。後日、お子さんが片手をあげて合掌の所作をしているのを見て、子は親の鏡だなと感じ、合掌は形だけではいけないなと反省したそうです。 6の「神社や教会で」の項目では、神さまに合掌? と不思議な気もします。宗派によって違いがあるそうですが、吉田さんは神社や教会など、どこへ行っても仏教の信仰する人を守る神様(守護神)として合掌するいるそうです。 7、8の項目に関して、つらいことや悲しいことに直面した時、追いつめられた時も思わず合掌してしまいます。亡き人への想いであったり、真剣に命に向き合う姿があります。 ○合掌とは? 『合掌の物語』エピソード募集のリーフレットが配られました。リーフレットには、『法華経』の「常不軽菩薩品(じょうふきょうぼさっぽん)第二十」について書かれています。 「不軽」という文字には、他者を軽んじないという意味が込められてます。 相手を敬い、他者の中に仏さまを見い出して、仏さまによって生かされている「いのち」に合掌をすることが基本とあります。 「相手とわかり合おう、分かち合おうという気持ちで合掌することで、自分の中の仏さまが磨かれます」と吉田さんはむすびました。
-

番外編「東京ジャーミイ訪問ツアー」
その他
2014-04-07
2014年3月15日(土)寺ネット・サンガ代表の中下大樹さん企画による「東京ジャーミイ訪問ツアー」が行なわれました。約30人の参加者たちは代々木上原駅に待ち合わせ、「東京モスク」と日本でも親しまれている「東京ジャーミイ・トルコ文化センター」に向かいます。 モスクはオスマントルコ様式で、1938年に建設されました。老朽化に伴い2000年に建て直されたそうです。 内装から外装までほとんどトルコから運ばれた資材を用いたという、青空に良く映える白い美しい建物です。 モスクに到着し、定例の「イスラーム入門講座」を受講しました。 日本人ムスリム・前野直樹さんからお話を伺います。 ○「40のハディース解説」第2回(第3の伝承)「イスラームの土台は五つの柱♪」 「六信五行」のイスラーム五行について詳しくお伺いしました。 五つの行いは、建物の五つの柱と喩えられており、大切なことなのだそうです。 五行・・・信仰告白(シャハーダ)・礼拝(サラー)・喜捨(ザカー)・断食・メッカ巡礼 五行は建物と同時に大樹にも喩えられるそうです。 唯一神のアッラーを意識しながら日々実践し、「心への水やりを忘れない」ことが大切というお話でした。 ○「40のハディース解説」第2回(第4の伝承)「運命を信じ、前向きに生きよう♪」 ハディースと呼ばれる言行録から「運命/宿命」をテーマについて、少し難しいお話に入りました。 レジュメには「運命は『予知』に基づき、自由意志による選択を追認して真実となる」とあります。 もし自分の自由意志によって間違った行ないをしたならば反省をし、よい選択を行なって結果が実ったならば、アッラーの恩恵と感謝します。 日々小さな実践によって信仰心を培っていくことの大切さを学びました。
-

寺ネット・サンガ「坊コン」「お坊さんあるある!」
坊コン
2014-04-05
2014年2月25日、寺ネット・サンガ「坊コン」が行なわれました。お坊さんが思わず「あるある!」と頷いてしまうようなお話を伺います。 本日のプチ法話は、八王子市延立寺のご住職、松本智量さんです。 ○予定は未定 急な用事が入ることが多いお坊さん。チケットの前売り券は買わず、旅行も急に中止になることを常に念頭に置いているそうです。 いつも「予定は未定」と語る松本さんは、先日雪の影響で交通機関が乱れた際、多くの方が怒っているのを知ってこんなことを考えたそうです。 自分の予定が絶対のものであると思っていると、予定通りにいかなかった時に何者かに侵害されたように感じ、被害者意識を持ってしまうこともあるのではないでしょうか。 そのことで、恨まなくてもいい人を恨んでしまうかもしれません。 ○思いのままにならない命を、私たちは生きている 日本人の平均寿命の80歳とされます。ほとんどの人は、自分はだいたいあと何年、何十年生きるだろうと「予定」を立てて生きています。 ところが、事故や病気など命が尽きる瞬間は、自分の都合を超えたところにあるのです。 自分の都合を離れてやって来る「死」さえ、私たちはコントロールしたいと願います。 「生老病死」という言葉の中で、「生」の文字から「自分の思い通りに姿に生まれなかった」という意味を知る時、同時に「思いのままにならない命を、私たちは生きている」ということを知ります。 予定や「こうであるべき」という理想に対してこだわりが強すぎると、知らない間に自分の鎖で自分を縛っているかもしれません。 ○コントロールしない 先日、松本さんが公道の脇に雪を除けていた時のことです。「お坊さんはみんな自分をいい人だと思っている」と語る松本さんは、この時も「一人で雪を除けた自分っていい人!」と思っていたそうです。 ふと、近所の方が声をかけてきました。きっと感謝の言葉かなと思ったところ……「そこに雪を置かないでくれる?」 これは意外な反応でした。一瞬、松本さんは怒りを感じたそうです。 すぐに「こういう方もいらっしゃる」と気持ちを切り替えました。自分のコントロールの範囲外であることを受け入れ、怒りの感情に捕われずに過ごすことができたそうです。 他人に対しても「この人はきっとこう言ってくれるだろう」と自分でコントロールしようとすると、異なる反応が返ってきた時に怒りや恨みが生まれます。 コントロールしないほうがラクなこともあるのではないでしょうか、と松本さんは語りました。
-

寺ネット・サンガ「坊コン」「お坊さんあるある!」
坊コン
2014-04-05
2014年1月14日(火)、寺ネット・サンガ「坊コン」が行なわれました。 今回のテーマは「お坊さんあるある!」です。 お坊さんが思わず「あるある!」と頷いてしまうことって何でしょう。普段、お坊さんって何をやっているの?お坊さんにも悩みがあるの? など、気になるテーマについて語り合いました。 本日の寺ネット・サンガ「坊コン」は、神奈川県平塚市の浄信寺のご住職、吉田健一さんのプチ法話から始まりました。 世の中にはたくさんの職業がありますが、「お坊さん」は謎が多い職業です。時間が決まっているわけではなく、お給料が決まっているわけでもない。売り上げなどの、何か見える成果が出ることもない。 吉田健一さんも、仕事なのか、生き方なのか、そこのところが難しいとおっしゃっていました。 お坊さんのお仕事といえば、お葬式や法事を思い浮かべますが、現代社会の中で儀式に対するニーズは小さくなっている傾向にあります。 お坊さん自身が社会の中で、自分たちの存在意義は何だろうと問われる時代になりました。 特に若いお坊さんたちの間で、積極的に社会に関わっていこうという動きが出ています。ニュースなどでもよく「お坊さん」に関する話題が上がります。 最近の「お坊さん」に関する報道の中で、吉田健一さんは「救う人・救われる人」という構図がみえてくると、それはちょっと違うと感じているそうです。 今はお坊さん側から、社会に対して何かを発信していかなければ、お坊さん自身の存在意義を保つことが難しくなっています。 死生観が失われつつある現在、社会にコミットしていこうと思いながら、どうコミットしていくかという点が現代のお坊さんたちの悩みでもあるそう。同じ時代に生き、悩みを持つ人々と一緒に問題意識を共有していきたい、というご自身の思いを語ってくださいました。 「同じ視線で語り合う、こういった場が大切ですね」と、寺ネット・サンガに集まった参加者の顔を見回しながらおっしゃっていました。 また、お坊さんと言えば「悩みをきいてくれる、解決してくれる」というイメージもあるかと思います。 吉田健一さんは「自死・自殺に向き合う僧侶の会」の活動もなさっています。自死・自殺も現代社会においては解決の難しい社会問題のひとつです。 例えば、病気になれば薬を処方される。一時的に良くなったとしても、薬に依存するようになっては、病気は根源的に解決されたとはいえません。 お坊さんに救いを求める人も、救われることに依存してしまうことが心配です。 人を救うのは、その人自身。 その人自身の自然治癒力を高め、「生きる力をどう引っぱり出すか」ということを大切にしていきたい、とご自身の方向性を語ってくださいました。
-

仏教ひとまわりツアー番外編
その他
2014-04-05
2013年12月17日(火)、目白の日本聖書神学校・メーヤー記念礼拝堂にて寺ネット・サンガ主催「仏教ひとまわりツアー番外編」が開催されました。 今回は教会でクリスマスについて知るツアーです。ツアー参加者と一緒にお坊さんたちも教会に集まりました。 日本基督(キリスト)教団新宿コミュニティー教会牧師の中村吉基(なかむらよしき)さんからお話を伺います。 日本では人口の約1パーセントほどしかいないキリスト教徒。中村牧師からキリスト教の歴史や教えについて、お話をお伺いしました。 教会と聞くとチャペルなど建物そのものを思い浮かべますが、日本で言う「講」と同じような意味で信徒の共同体のことを「教会」と呼ぶのだそうです。 新約聖書の冒頭には、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4つの福音書というキリストの言行を描いた文書があります。マルコによる福音書が一番古く、紀元65年~70年ぐらいに記されたと考えられています。 クリスマスについての記述は、この福音書のどこに記されているのでしょう。 中村牧師は代表的な2つの物語を読み聞かせてくださいました。 ・ルカによる福音書2章から、生まれたばかりのイエスが飼い葉桶に寝かされているのを天使のお告げを受けて探しにきた羊飼いと対面する。 ・マタイによる福音書2章から、占星術の学者たちが星に導かれて幼子イエスに対面し、贈り物をささげる。 生まれたばかりのイエスに最初に出会った人たちは、貧しい羊飼いやユダヤ人から忌み嫌われていた異邦人の占星術師など社会的に虐げられていた弱い立場の人たちでした。そして聖書の中のイエス降誕物語の中には12月25日という日付は出てきません。 そこで12月25日という日付について、中村牧師からお話がありました。 かつてローマ帝国時代、ミトラ教という太陽神を崇める信仰が流行していました。ちょうど冬至の頃、太陽神が生まれた日としてお祭りをしていたそうです。12月25日のクリスマスは、このお祭りに「義の太陽」であるキリストの誕生を重ね合わせたのが起源だと言われています。 またエジプトのクリスチャンたちは、神話の中のオシリス神のお祭り1月6日をイエス降誕の日としてお祝いしていました。 西暦325年に、ニカイヤ教会会議にて12月25日をイエスの降誕を記念する日と定めます。聖書の暦では日没から次の日の日没までを一日と数えますので、12月24日の日没からクリスマスに入ります。 その一方で1月6日をクリスマスとして大切にしている地域もあり、多くのキリスト教国では12月25日から1月6日までをクリスマスシーズンとしてお祝いするのがポピュラーなのだそうです。
-

第14回 仏教ひとまわりツアー「お骨の行方」 無縁墓地
仏教ひとまわりツアー
2014-04-05
2013年11月9日(土)、多磨霊園そばの蓮宝寺にて寺ネット・サンガ主催「仏教ひとまわりツアー」が行なわれました。前回に引き続き「お骨の行方」のテーマで、多磨霊園内の墓地をお参りしながら無縁墓・合祀墓について考えます。 まずは蓮宝寺の副住職小川有閑さんよりお話を伺いました。 多磨霊園は大正12年に開園した国内初の都市計画共葬墓地です。多磨霊園でお墓をお持ちの方の気持ちに寄り添いたいと、この地に昭和28年に蓮宝寺は建立されたそうです。 檀家としてのお付き合いのない方に霊園で供養を頼まれることが多く、短い会話の中で故人の話をしたり説法をする難しさを語ってくださいました。 小川有閑さんは現在、多摩武蔵野地域での生老病死のトータルサポートに関する活動「ライフエンディング研究会」を立ち上げエンディングノートを作るなどの活動をしています。 葬祭業・石材店・保健師・医師などの専門家と僧侶が一緒になって、生老病死のトータルサポートができるように、まずは相談の窓口になりたいという思いがあったそうです。 平均寿命が延びる一方で、介護の必要な高齢者が増えています。 また、お墓の需要も今後ますます増えていくことが予想されます。 ライフエンディングに関するサポート体制を徐々に充実させていきたいと、今後の活動について語ってくださいました。
-

寺ネット・サンガ「坊コン」「お骨の行方」
坊コン
2014-04-05
2013年10月21日(月)、寺ネット・サンガ「坊コン」が行なわれました。 今回のテーマは「無縁仏について」です。 プチ法話「お骨の気持ち」というテーマで永寿院の吉田尚英住職のお話を伺います。 まず、お墓は何のためにあるのでしょうというお話から始まりました。 最近は少子化の影響を受けてお墓の継承が難しくなり、自分の入るお墓やお墓の今後に不安を抱く方が増えています。 お墓があってお骨の行方が決まり、安心して晩年を過ごすことができるという方もいます。 また、お墓は故人との対話の場であり、祈りの場でもあります。 亡き方にとって魂が宿るお骨やお墓は依代(よりしろ)であり、縁のある人たちが故人を偲ぶ大切な場所でもあります。 永寿院の境内には古墳があります。古墳からは約1500年前のご遺骨や遺物が発掘されました。 故人と縁のある人が世を去って世代が移り変わっても、お墓は歴史や文化を未来へ遺す大切な場所となります。 お墓を通じて、私たちはその当時の人々の生活や心を想像し、また現代を生きる私たちも同じように様々な思いや文化を未来に受け渡すことができます。 無縁墓に眠る方々も、それぞれのかけがえのない人生があったはずです。 お骨の気持ちを考えながら私たちがお祈りしている時には、きっと眠っている故人やご先祖さまも喜んでいるのではないでしょうか。 吉田住職はご自分が亡くなった際に、お参りしてもらえたらうれしいいだろうなと考えながら、日々おつとめをされているそうです。
-

第13回 仏教ひとまわりツアー「お骨の行方」 樹木葬
仏教ひとまわりツアー
2014-04-05
2013年9月1日(日)八王子市川口町の延寿院にて、寺ネット・サンガ主催「仏教ひとまわりツアー」第4段『お骨の行方』が行なわれました。 今回のテーマは樹木葬です。 里山型樹木葬墓地「東京里山墓苑」について、延寿院ご住職の及川一晋さんよりお話を伺います。 及川住職が延寿院のご住職になられたのは平成8年のこと。新宿からこの川口町を初めて訪れた時、豊かな自然を感じて「いいなあ」と思ったそうです。 このあたりの里山はコナラなどの広葉樹が生い茂り、かつて近所の農家さんたちは落ち葉を肥料にし、里山から薪を取って生活していました。しかし安価な外材輸入が始まると、やがて里山は放置され、笹やぶだらけの荒れた山になってしまったそうです。 樹木葬の形態として、区画を購入して骨壺で埋葬する「個人墓」、合祀して埋葬する「合祀墓」、また無縁仏としてお地蔵さまのもとに眠る「無縁墓」があります。 いずれのお墓も住職が日々供養なさって、遺族の方はいつでもお墓参りができます。 「人々の願いに寄り添うスタンスで」とおっしゃていた及川住職は、お墓の継承問題、孤立死問題など社会的な背景と環境保全の観点から、約3年の年月をかけて「東京里山墓苑」を開設されました。 人と自然とつながりを感じ、また自然に感謝しながら、人も自然の中で循環していく新しいお墓の形態です。
-

第12回 仏教ひとまわりツアー「お骨の行方」
仏教ひとまわりツアー
2014-04-05
8月2日(金)、寺ネット・サンガ第12回「仏教ひとまわりツアー」第4段「お骨の行方①」が築地本願寺にて行なわれ、当日は48人の参加者が講堂に集まりました。 築地本願寺について、八王子市延立寺の松本智量住職にご案内いただきます。 築地本願寺は1657年明暦の大火の被害を受けて、浅草から築地に移転しました。 その際、佃島(つくだじま)の門徒が海を埋め立てて「地を築いた」ことから「築地御坊」という名称で親しまれてきましたが、1923(大正12)年に関東大震災の火災で本堂が焼失。 再び焼失することがないようにと、現在の古代インド仏教様式の石造りの本堂が建築家伊東忠太氏により設計され、築地本願寺は1934(昭和9)年に落成します。 松本ご住職のご案内で、納骨堂と本堂を参拝させて頂きました。 当日は築地本願寺の盆踊りが行なわれていましたので、ご本尊の阿弥陀如来さまに手を合わせる参拝者の方が多くいらっしゃいました。 「仏教ひとまわりツアー」参加者も合掌しお参りしました。
-
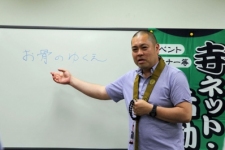
寺ネット・サンガ「坊コン」「お骨の行方」
坊コン
2014-04-05
7月5日(金)に寺ネット・サンガ「坊コン」が行われました。今回のテーマは「お骨の行方」。神奈川県平塚市 浄信寺のご住職吉田健一さんのお話です。 ○お墓の歴史とお骨について 日本人が「お墓」ときくと「先祖代々の墓」を思い浮かべます。 日本で火葬が行われ、現在の四角い墓石に「○○家の墓」と刻まれている先祖墓が一般化したのは戦後で、それまで日本では土葬が中心でした。 民俗学者の柳田国男氏が昭和4年に『葬制の沿革について』の中で、特に西日本で顕著な傾向を示す「両墓制」について述べています。 「両墓制」とは、遺体や遺骨を埋葬した「埋め墓」と、別の場所に「拝み墓」(詣り墓ともいう)という2つのお墓を建てる形式です。拝み墓は御魂(みたま)の依代(よりしろ)と考えられます。昔の日本では遺骨と御魂は別であるという感覚を持っていたことがわかります。 日本人が遺骨と御魂の関係を強く意識する傾向は、終戦後に顕著になったのではないかとも考えられます。 日本人が国外で亡くなった場合、遺骨をふるさとの日本へ戻そうとする気持ちが強いといわれます。 国外の亡くなった場所の具体的な地名が意識され、同時にその土地に御魂がさまよっているような感覚を覚えます。遺骨が戻ってくれば、その方の御魂も国に戻ってくる、そんな意識が日本人の中にはあるようです。
-

第11回 仏教ひとまわりツアー 尼僧さんと一緒に浄土めぐり
仏教ひとまわりツアー
2014-04-05
梅雨を忘れさせる晴天に恵まれた6月8日。寺ネット・サンガ「仏教ひとまわりツアー」が行なわれ、柴又帝釈天「題経寺」に約40名の参加者が集まりました。 ○帝釈堂でご開帳の法要 初めに帝釈堂内にて、「板本尊(いたほんぞん)」のご開帳法要に参列。「仏教ひとまわりツアー」参加者のお名前を読み上げて祈願をして頂きました。 板本尊の片面には日蓮聖人ご真刻の「病即消滅本尊」の経文が、もう一方の面には帝釈天王が彫刻されています。 お経中に一人ひとり板本尊を間近にお参りさせていただきました。 暗い堂内に帝釈天王の像がぼんやりと浮かぶように照らされています。お顔をはっきりとは拝見することができないほど暗い中で、掲げた剣と大きく開いた左手が見えます。闇の中にヌッと帝釈天様が立っているような感じです。 たいへん貴重な体験で、おそらく今後もこのような機会はめったにないことであると、忘れられない思い出になりました。 ○題経寺 境内ツアー 境内の案内ガイドは、池上本門寺にて池上市民大学の副担任をなさっている岡本亮伸さんです。 ・柴又帝釈天 経栄山題経寺は、江戸時代初期・寛永年間の創立のお寺です。 帝釈天王の像が彫刻された板本尊が一時所在不明となっていましたが、安永8年春、庚申の日に再び姿を本堂棟上から発見され、「病即消滅」の板本尊が出現した庚申の日に縁日が盛んに行なわれるようになりました。 1969年に公開された「男はつらいよ」の寅さん人気が高まり、柴又の町は現在も多くの参拝客と観光客で賑わっています。 ・彫刻ギャラリー お開帳をいただいた帝釈堂内陣の外壁には、ぐるりと繊細な彫刻が施されています。 現在は彫刻の保護のためにガラス張りになって、回廊を歩いて彫刻を鑑賞することができます。法華経の説話にまつわる場面を欅(けやき)の一枚板を彫刻した、貴重な文化財の数々です。 岡本さんのガイドで拝見していると、物語を見て歩いているような気分になります。 薬草から薬を作っている場面が描かれ、法華経が人々の心の病を治す良薬であることを表している「薬王菩薩本事品(やくおうぼさつほんじほん)第二十三」の「病即消滅の図」が心に残りました。 ・大庭園(邃渓園・すいけいえん) 日本庭園を眺める大客殿では、日本最大の大南天の床柱などを拝見しました。いたるところに職人魂が宿っている境内で、私たちはしばしば足を止め、じっくりと彫刻や床柱に見入っていました。
-

寺ネット・サンガ「坊コン」「孤立死」ひとりで死ぬということ
坊コン
2014-04-05
今回の坊コンは、寺ネット・サンガ代表の中下大樹さんのお話です。 新潟県長岡市のホスピス(緩和ケア病棟)で、末期がんの患者さんたちを多く看取ってきた中下さんは、現在、独り暮らしのお年寄りの見回りや、自死を考えるまで追い詰められている方々の相談窓口など、自死や孤立死に関する問題について様々な活動に従事なさっています。 お話の前に、以前放送されたテレビ東京のドキュメンタリー番組「独りで死ぬということ」を30分間拝見いたしました。 スクリーンに映し出されたのは、将来、孤立死が心配されるお二人の女性。 若い時にトラブルに巻き込まれ、以来人を信用できなくなってしまった女性は長い間家に独り引きこもって暮らしています。世間とのつながりは「携帯電話だけだよね」と語り、自身が高齢となった今「死ぬのを待つだけ」と中下さんにその心情を吐露します。 もう一人は、夫に先立たれ、現在一人で病と闘いながら自宅で独り暮らしている女性です。子どもがいないため、せめて夫の七回忌までは生きようと目標を語りますが、番組の途中で病が悪化して入院してしまいます。お見舞いに訪れた中下さんに、彼女は「もう無理かもしれない、しかたがないね」と弱々しい声で話すのでした。 世間とのつながりを自ら断ち、何をするのでもなくただ死期を待つだけの「孤独」。一方では先立った大切な人のために、自分の命をなんとかつなごうとしながら、不安だらけの日々を過ごす「孤独」があります。 場面は変わり、世間とのつながりを断った女性を久しぶりに散歩へ誘い、公園で中下さん、女性、反町先生の3人が並んで腰かけています。 番組には、今回の「坊コン」にも出席されていた法医学者の反町吉秀先生(大妻女子大学大学院人間文化研究科教授)も出演されていました。 中下さんは遠くを見つめながら、女性に問いかけます。 「独りで死ぬことってどう思う?」 女性は表情を変えることなく、しっかりとした口調でこう言いました。 「なんともないね!」 少し間を置いて出た、この言葉は衝撃的でした。 生きることと死ぬことを同じように、彼女は自分の「生」も「死」も、ただ時間の流れに任せているように思えました。 スクリーンに映し出された女性の表情から本心を読み取ることはできませんが、言葉を発する少しの「間」は何を物語っていたのでしょうか。
-

第10回 仏教ひとまわりツアー 尼僧さんと一緒に浄土めぐり
仏教ひとまわりツアー
2014-04-05
本日ツアーのガイドをして下さったのは、光善寺の坊守(お寺の奥様)柳川眞諦(やながわしんたい)さん。 柳川さんは、お寺に嫁いでからご修行をお積みになり、現在は浄土真宗本願寺派の布教師として活躍していらっしゃいます。 ピンクの艶やかな法衣で登場された柳川さんに、私たちの目はくぎ付けになってしまいました。 法衣も浄土のお荘厳(お飾り)の一つなのだそうです。 ご本尊の阿弥陀如来さまの周りは金や極彩色で彩られた蓮の花が描かれており、僧侶も含めたお堂全体で浄土を表しています。 浄土真宗は、阿弥陀如来さまの本願力(慈悲と智慧の働き)によって、人間の命が尽きたら、即浄土に往生という教えです。お釈迦さまの説かれた「浄土三部経(じょうどさんぶきょう)」という経典に基づく教えです。 ○浄土三部経 阿弥陀如来さまは別名無量寿如来(むりょうじゅにょらい)といい、『仏説無量寿経(ぶっせつむりょうじゅきょう)』は浄土真宗では一番重要な経典とされます。 『仏説観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)』にはインドのマガタ国で起こった悲劇をもとに、お釈迦さまがお念仏によって往生する方法をお説きになっています。 その中には、韋提希夫人(いだいけふじん)という王妃さまが登場してきます。 自分の過去の過ちを忘れ、現在の自分の身の上の不幸ばかりを嘆く王妃さまの姿は、煩悩を抱えて悩み苦しむ人間の代表として描かれています。 『仏説阿弥陀経(あみだきょう)』は、今回私たちも一緒にお唱えいたしました。 阿弥陀経は智慧第一といわれた舎利弗(しゃりほつ)というお弟子さまに語りかける形で綴られています。 問答形式ではなく、無問自説といって、お釈迦さまが自ら説かれる形式で進んでいきます。
-
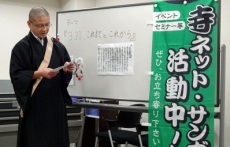
寺ネット・サンガ「坊コン」「3.11これまでとこれから」
坊コン
2014-04-03
2011年(平成23年)3月11日に起きた東日本大震災から、まもなく2年が経とうとしています。 寺ネット・サンガ「坊コン」では、震災をいつまでも語り継いでいくことの大切さに焦点をあて、東日本大震災をテーマに語り合いました。 プチ法話担当は、永寿院の吉田尚英住職です。 歴史の教科書で馴染みのある日蓮聖人の『立正安国論』は、旅人と宿の主の問答形式で話が進み、全部で十の問答で構成されています。その冒頭には災害や飢饉に苦しむ鎌倉時代の人々の様子が綴られています。 文応元年(1260)に北条時頼に上呈されましたが、同時代に編纂された『吾妻鏡』には、数年前から地震・暴風雨・洪水など天災が続いたことが記録に残っており、巷には犯罪者や疫病の流行、飢饉に苦しむ人々が溢れていたとあります。 日蓮聖人の建治4年(1278)『松野殿御返事』(まつのどのごへんじ)の中には、人肉を喰らう者もいたと衝撃的な文章が残されており、鎌倉時代には想像を超える悲惨なありさまが広がっていたようです。 『方丈記』を綴った鴨長明も、養和2年(1182)4・5月、左京だけで4万2300人ほどの死者の数を数えたとあり、日本中に大変な苦しみ、悲しみが溢れていたことがわかります。 今生きているこの娑婆世界が浄土であり、浄土を生きる私たちは生きながら仏にもなることができる。しかし、一瞬の心の中には仏もいれば鬼もいる。一瞬のうちに浄土と地獄を行き来するのが私たちです。 信じることがすべての救いではなく、仏さまを信じることによって心の安定を図り、正しい心によってこの世を浄土にしていこう。迷いの根源的な問題から目を逸らし安楽へ導くのではなく、厳しいながら確実な方法を示しているのが日蓮聖人の教えです。 日蓮聖人はご自身が先のお手紙からうかがい知れるように、苦しみの体験者であり目撃者でもあったということがわかりました。


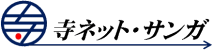
寺ネット・サンガのイベント
「坊コン」
オフィス街でお坊さんとコン談!コン親!コンパ!急な参加も歓迎!定番人気の仏教入門イベントです。
「仏教ひとまわりツアー」
お坊さんたちと一緒に仏教ワクワク体験イベント!宗派宗教を超えて、次はいずこへひとまわり?
「その他の特別イベント」
番外編の特別イベントです。楽しんでいただけたかな?またの機会をお楽しみに!