寺ネット・サンガ 過去のイベント一覧
-

日本橋七福神めぐりの報告です
仏教ひとまわりツアー
2025-03-29
桜も咲き始めたお天気の良い日、寺ネット・サンガのお坊さんと皆さんとで日本橋七福神を巡りました。 七福神巡りは、思いがけない地元の歴史を発見したり、多分一人では行かないだろうというような寺社にご縁をいただきながら、当時からの信仰や文化と触れる楽しい機会となります。 看板を読み合ったり、知ってることを伝えあいながら楽しく歩きました。 今回まわった順序は以下の通り 水天宮(弁財天)→松島神社(大国神)→末廣神社(毘沙門天)→笠間稲荷神社(寿老神)→椙森神社(恵比寿神)→小網神社(福禄寿)→茶の木神社(布袋尊) 終わってからはお約束のお疲れ様の一杯です。 下町の雰囲気のお店で冷たいビールやホッピーを美味しくいただきました。 また、どこかの町の七福神を回る予定です。 日本橋七福神めぐりの動画 https://youtu.be/8HZfkzX9KuI
-

7/31横須賀で『軍港めぐりクルーズ』寺社めぐりの報告
仏教ひとまわりツアー
2024-08-04
今回は暑気払いを兼ねて横須賀からクルーズ船に乗り、潮風に吹かれながら45分間の軍港めぐりに参加しました。 その後、有名な「どぶ板通り」を歩き「延命地蔵尊」や、108段以上の石段を上った先の「豊川稲荷」にお参りして汗をかき、 最後にみなさんで冷たいビールをいただいてきました。 延命地蔵尊はどぶ板通りの中にありますし、 豊川稲荷と、今回は寄らなかったですが諏訪大神社も 街中の商店街の中からすぐに参道に入れるのに、結構な階段があり、 登りきると木々が多く視界が開けて街中とは思えないような場所です。 どぶ板通りのアメリカの伝統的なスタイル・ネイビーバーガーや スカジャンのお店が並ぶ雰囲気と その中に点在する寺社の対比が面白い場所でした。 潜水艦やイージス艦を見学しながら、 仏教の考え方で平和が築かれていくことを思いました。
-

サンガの遠足「武蔵国分寺跡を訪ねて」
仏教ひとまわりツアー
2023-04-21
4/19(水) 寺ネットサンガの遠足 「武蔵国分寺跡を訪ねて」が行われました。 2023年の春になり、やっとコロナ禍も落ち着きをみせてきました。そして、念願の寺ネット・サンガの遠足イベントも再開の運びとなりました。 今回は奈良時代をしのび、武蔵国分寺跡・国府跡等を訪ねる小旅行です。 西国分寺駅を2時に出発し、東山道(とうさんどう)武蔵路(むさしみち)の遺構を見学しながら国府跡を訪ね、府中の大國魂神社へと3時間ほど歩きました。 国分寺市学芸員の先生にご案内をいただき、汗ばむほど晴れた午後のひと時、遠く奈良時代の仏教文化へ想いを馳せながらのお散歩です。 西国分寺駅の東南には7世紀に整備されたという東山道武蔵路跡が見つかっています。 まずは、その東山道の遺構が展示されている所へと向かいました。 当時としては最新の国レベルの道路網の整備は、今でいう高速道路レベルの道路をつくることに匹敵します。七道といわれた各地方へ、都にいる天皇からの伝令を伝えるためや、税納の物資の運搬として使われたのだそうです。情報伝達の為に駅家(うまや)を16キロごとに設置し、そこに道路の重要性に応じて、10頭から20頭の馬を置いていたのだそうで、しっかりとした情報伝達ネットワークが作られて行ったのは当時の政治の推進力を物語っています。
-

サンガの遠足 in 目黒
仏教ひとまわりツアー
2019-09-07
江戸時代、多くの参拝客を集めた目黒不動瀧泉寺。 現在はマンションが立ち並ぶ門前町ですが、かつては500メートル以上、左右に参拝客目当ての商店が軒を連ねたといわれています。 伝教大師最澄の弟子で、天台三代座主となった慈覚大師円仁が、比叡山に向かう途中この地で宿をとった際、不動明王の夢を見たので、その像を彫ったのが寺の始まりだといわれます。 江戸時代には、三代将軍家光公の鷹狩りが縁で、将軍家や大名家の加護を受け、江戸近郊の参詣行楽地として栄えるようになりました。 境内には、多くのお堂や仏像のほか、慈覚大師ゆかりの「独鈷の瀧」や、家光の鷹狩りゆかりの「鷹居の松」など、様々なご利益があるお参りどころが盛りだくさん。 さすが、江戸庶民に人気の参拝地でした。
-

寺ネット・サンガの遠足 in横浜
仏教ひとまわりツアー
2019-04-19
平成の最後の月となった4月。好評の寺ネットサンガの遠足が17日(水)に行われました。 今回は横浜市旭区近辺を散策します。 1950年代ごろから、横浜市中心部や京浜工業地帯への通勤者のベットタウンとして宅地化が進んだ旭区は、寺ネットサンガの代表である吉田尚英さん故郷であり、吉田さんの実家本立寺を訪ねます。今日は吉田さんご推薦の帷子川~導水道の緑道を主に歩いていきます。 旭区近辺は1950年代から宅地化が進み、起伏にとんだ地域に途切れなく市街地が形成されていきました。土地の造成と共に人口が激増し、1969年10月1日には保土ヶ谷区から旭区が分割新設されました。出発点の「鶴ヶ峰」は昔、よく鶴が飛来したことから土地の名前がついたのだとか。配られたイヤホンガイドで吉田さんの説明を聞きながら、閑静な住宅街を帷子川へと向かいます。 〇鶴ヶ峰~帷子親水公園 曇天の微風の中、鶴ヶ峰駅を出発して帷子川親水公園へと向かいました。ソメイヨシノは葉桜になっていましたが、八重桜が五分咲きくらいで華やかなピンク色に川面を染めています。公園内の新緑にひらひらと舞う桜の花びらがまた良い風情。帷子川の川沿いにまだ残る桜花を愛でながら歩いていくと、山の手で鶯のさえずりが聞こえます。帷子川の浅瀬にはコサギや鴨の姿も見られました。
-

サンガの遠足~多摩川台古墳群と等々力渓谷
仏教ひとまわりツアー
2018-10-03
大好評の「サンガの遠足」が2018年9月28日(金)に行われました。今回は多摩川駅から等々力渓谷辺りを5キロほど歩いていきます。 実は、田園調布から等々力にかけてのこの辺りは、東京有数の古墳群のある場所。なんと50基もの古墳が発見されています。この多摩川を見下ろす台地は、さながらエジプトの王家の谷の様。田園調布古墳群と野毛古墳群という二つの古墳群を総称して、荏原台古墳群とよばれるこの辺りを散策していきます。 今回のサンガの遠足では、石造文化財調査研究所代表である考古学者の松原典明さんに同行をお願いすることに。松原先生は寺ネットサンガの吉田代表のご自坊である永寿院敷地内にある古墳の発掘や、万両塚の調査を担当された考古学者です。専門家のイヤホンガイドで解説付きという贅沢な遠足が実現しました。 〇多摩川駅~浅間神社古墳へ 連日の雨や台風でお天気が心配されましたが、当日は何日かぶりの晴天に。汗ばむ陽気の中、午後一時に駅を出発しました。目指すはすぐ近くの浅間神社古墳。約6世紀頃の築造とされる田園調布古墳群では一番南東端にあたる前方後円墳です。 高台の浅間神社から多摩川を眺めると、グリーンの丸子橋と東横線の線路が対岸の武蔵小杉のビル群へと続いているのが見えます。古墳時代の多摩川は、現在とは違ってくねくねと蛇行していたそう。古代の多摩川はどんな様相だったのでしょう。吉田さんがそんな多摩川の河川敷を眺めながら「ここはシンゴジラという映画のロケ地となった辺りです。ここが自衛隊の指揮所になったところですよ」と面白情報を教えてくださいました。 実は、浅間神社の下が前方後円墳の後円部分にあたるのだそう。 皆で小高く盛り上がった浅間神社のお社に参拝してから、神社の裏手に回ってみました。そこには金網越しに東横線の線路が。ちょうど古墳の前方部分は線路の下になるのだそう。 金網越しに眺めましたが、古墳の名残りも見当たらず残念。
-

サンガの遠足~鎌倉part3
仏教ひとまわりツアー
2018-06-01
寺ネット・サンガの新企画「サンガの遠足」の第3弾が2018年5月28日(月)に開催されました。 3回目の今回は江の島が見える海辺周辺を散策。極楽寺~鎌倉大仏~由比ヶ浜~材木座海岸~光明寺というコースで歩いていきます。 集合場所は江ノ電の途中駅である「極楽寺」。雨が心配されましたが曇り空から時折お日様が顔出すというまずまずのお天気の中、出発です。 〇極楽寺にて 今年は紫陽花の開花が通常よりも早く紫陽花がそこかしこで咲き始めていて、極楽寺の山門前にも紫青やピンク色に色づき始めた紫陽花がきれいでした。 今回のサンガの遠足は、鎌倉散策のベテランガイドの大貫昭彦さんが同行くださいます。まずは極楽寺山門前で極楽寺の由来からお話しいただきました。 大貫さんはなんと御年80歳。国語教師をされていたとのことで、退職後にガイドのお仕事を始められたのだそう。お年を全く感じさせないかくしゃくとした立姿で、活舌よく、また大変わかりやすい。しかも、細かい数字や人物名も暗記していらっしゃるのには本当に驚きました。 極楽寺を開山した忍性さんが日蓮聖人と雨ごいの闘いをして忍性さんが負けてしまった話や、忍性さんが病人や貧者などの為に尽力した話、極楽寺が火事にあって再建しなければならない時に、どのように資金を集めたかなどお話しくださいました。その当時に今で言う社会福祉や病院としての役割を寺院にもたらした忍性に、とても興味を持ちました。 さらに極楽寺にある寺宝、重要文化財仏像の釈迦如来像や十大弟子像を拝観しました。釈迦如来坐像は転法輪印の手の形が大変優雅な釈迦様です。 秘仏である釈迦如来立像をお参りすることはできませんでしたが、水の流れるような同心円で衣をあらわす清凉寺式仏像の特徴と、鎌倉時代の深彫りの仏像の違いをご教授頂きました。 十大弟子像はそれぞれが個性に溢れ、謂れに基づいて造られていて興味深く参拝しました。仏像には玉眼が施されているので、少しの光でもキラキラと輝き命が宿っているよう。 参加者のみなさんも座って下から眺めたり、顔を近づけてみたりしながら仏像をお参りしていました。
-

4/22(日)寺町ウォーキングin大阪
仏教ひとまわりツアー
2018-04-23
寺町ウォーキングin大阪。 平成30年4月22日(日)12時に、寺ネット・サンガ事務局員の青木隆興さんが住職をしている大阪市天王寺区の興徳寺に集合。 初の大阪でのイベントということで参加者がどれだけ集まるか不安ではありましたが、東京から6名、関西から2名の計8名、和気あいあいと歩くことが出きました。 初夏の晴天にも恵まれ、気持ちよく大阪の寺々をお参りさせていただきました。 興徳寺では青木住職より古地図の屏風をもとに、大河ドラマで有名になった「真田丸」が興徳寺の門前であったということや興徳寺と真田丸の関係についてお話しいただきました。
-

第2回寺町ウォーキング~樹木葬と永代供養墓めぐり(後編)
仏教ひとまわりツアー
2016-04-06
第2回寺町ウォーキングのこの日、4月2日(土)は「五重塔まつり」 重要文化財の五重塔が特別開帳される日で、奉安されている仏様の御前で御祈祷を受けることが出来ます。曇り空でしたが桜の花も満開となり花も見頃で大勢の参拝客でにぎわいました。 今回のウォーキングには、永代供養墓めぐりのなかに「五重塔まつり」の法要もスケジュールに組み込まれているので、間近でゆっくりと法要参拝することが出来ました。今年は楽しみにしていた散華がなくて大変残念でしたが、見事な桜を愛でながら法要を見ることができ、参加者の皆さんもとても満足そうです。
-

第2回寺町ウォーキング~樹木葬と永代供養墓めぐり(前編)
仏教ひとまわりツアー
2016-04-06
2016年4月2日(土)に日蓮宗東京都南部宗務所主催、寺ネット・サンガ協力の「歩いて終活 寺町ウォーキング第2回」が開催されました。日蓮宗のお坊さんと共に、様々なお寺を巡りながら終活について考えましょうというイベントです。 第2回目の今回は池上本門寺周辺を歩きます。この日の本門寺は丁度「五重塔まつり」の開催日。朝方降った雨も上がり、満開の桜が私たちを迎えてくれました。 第2回寺町ウォーキングの出発地点は日蓮聖人ご入滅の霊場、大坊本行寺(だいぼうほんぎょうじ)。鶴林殿にて開講式が行われ、今回も主催の日蓮宗東京都南部宗務所の石井隆康所長が導師となり、事故のないように祈願・回向をしてくださいました。参加者の皆さんと共にお題目をお唱えし、心も晴れ晴れと準備万端です。 ○プチ講演「だれがお墓を守るのか?」 今回の終活テーマは、「お骨とお墓『お骨の気持ちでお墓めぐり』」 南部宗務所のお坊さん達と一緒に、樹木葬や様々なコンセプトの永代供養墓をめぐって、お墓について歩きながら考えます。 今回はウォーキング前にまず、第一生命経済研究所の小谷みどり氏の講演「だれが墓を守るのか」を拝聴しました。高齢世帯の核家族化や配偶者や子供のいない高齢者が増えているといわれている昨今のお墓事情についてのお話です。 お墓を継承する人がいないことによる無縁墓の増加は、地方だけではなく都市部でも問題になっているようです。一方で、死者と生者の対話の場として、精神的な支えともなっている面もお墓にはあります。と小谷さんは説明くださいました。 確かにお墓参りに行くことでなんとなく安心感や先祖とのつながりを感じ、今の自分の存在を感謝の気持ちをもって前向きに生きていくことができる気がします。お墓は納骨という場だけでなく、遺された者の為にもあるのではないかと考えさせられました。将来、お墓の多様化で、今よりももっと選べるお墓の選択肢が増えていくのでしょう。
-

「歩いて終活 寺町ウォーキング」(後編)
仏教ひとまわりツアー
2016-02-09
立会川緑道は、碑文谷池と溝水池を水源とする立会川の上を緑道としたもので、暗渠となってしまった川の跡をたどることが出来るようになっています。道路より一段高く整備されているので散歩道として最適な場所です。 今回のウォーキング中間地点である天台宗の円融寺(えんゆうじ)へ到着すると、参道には紅梅が咲き誇り爽やかな香りを漂わせていました。 “碑文谷の黒仁王“といわれる円融寺の金剛力士像は、東京都指定文化財。また、釈迦堂にいたっては都内最古の木造建築の釈迦堂で、国の重要文化財に指定されているものです。 円融寺では思わぬ幸運に。 普段は閉じている釈迦堂に入れていただき、釈迦如来をお参りしました。 もとは日蓮宗だったというお寺の由来や建築様式などの説明を受け、その後、休憩室で美しい竹林を眺めながらお茶を頂きました。こんな静かな時間が過ごせるなんて、都会の真ん中とは思えないほどです。 円融寺でのひと時の休憩の後は、碑文谷付近を通り“すずめのお宿緑地公園”へと向かいます。 碑文谷は目黒区でも古い歴史を持つ地域。筍が目黒名物だったころの名残の竹林がこの緑地公園内で見る事が出来ます。公園内にある古民家も見学し、懐かしい昔の囲炉裏や、薪、かまどなどを拝見しました。 次は最終目的地、都立大学駅近くにある立源寺へと向かいます。
-

「歩いて終活 寺町ウォーキング」(前編)
仏教ひとまわりツアー
2016-02-09
2016年2月6日(土)に日蓮宗東京都南部宗務所主催、寺ネット・サンガ協力という形で「歩いて終活 寺町ウォーキング」が開催されました。 終活やエンディングに取り組んできた寺ネット・サンガとして企画・集客に協力をしており、「仏教ひとまわりツアー」の番外編に位置付けています。 今回は日蓮宗のお坊さん達と一緒にウォーキングしながらお寺を巡り、最後にはお棺に入ってみましょうというもの。 お坊さんと一緒に歩くこともあまりできない体験ですが、更に入棺体験とは!一体どんなイベントになるでしょう。わくわくしながら集合場所の法連寺(ほうれんじ)へと向かいました。 法連寺での開会式では、主催の日蓮宗東京都南部宗務所の石井隆康所長が導師でおつとめをして、事故のないように祈願・回向をして頂きました。 その後、永寿院の吉田尚英住職によるオリエンテーション。 スケジュールとウォーキングの注意点などに加えて、終活の目指すところは臨終の瞬間ではなく、その先の仏の国であることを今日の体験の中で感じてほしいと、文字通りオリエンテーション(進路を示す)をしていただきました。 日蓮宗東京南部宗務所主催のイベントですが、寺ネットサンガからの参加者も多数ありました。「寺町ウォーキング」で、歩きながら日蓮宗のお坊さんに終活の相談に乗ってもらうのもいいですね。
-

仏教ひとまわりツアー 八王子の萌え寺?!「了法寺」
仏教ひとまわりツアー
2015-10-29
仏教ひとまわりツアー第7段は「深遠(ディープ)な寺めぐり ~甚だ深い仏の教え、そーっとのぞいてみませんか?」をテーマにした、ちょっとユニークなお寺めぐりツアー。その第2回が2015年10月24日(土)、西八王子にある日蓮宗の松栄山了法寺にて開催されました。 了法寺は「萌え寺」として全国にその名を知られているお寺です。可愛い美少女アニメのキャラクターを看板に採用したことから、ネット世界で口コミで広がり、今や日本国内だけでなく海外からも注目されています。 了法寺がなぜ「萌え寺」と呼ばれるようになったのかという疑問符を、頭いっぱいに抱えながら実際にお寺に行ってみると・・・例の萌え系キャラの看板が! その看板を横目に見ながら境内へ至る参道を歩きましたが、静かな落ち着いた佇まいの一見普通のお寺ではないですか。少し期待を裏切られた感に、こころもち残念に思いながらも・・・ご住職がもしかしたら?!などと想像を膨らませながら境内を入って行きました。 果たして!いやはや普通に袈裟を纏っておられるお坊様が、ニコニコと優しく出迎えてくださったのであります。
-

仏教ひとまわりツアー 港区「明王院」護摩祈祷
仏教ひとまわりツアー
2015-08-31
寺ネットサンガ主催の人気企画「仏教ひとまわりツアー」も第7段を迎えました。第7段は「深遠(ディープ)な寺めぐり ~甚だ深い仏の教え、そーっとのぞいてみませんか?」と題して、色々な体験を盛り込んだ、ちょっと深めなお寺めぐりツアーです。その第1回が2015年8月29日(土)、港区三田の真言宗のお寺、五大山明王院不動寺にて開催されました。 真言宗と言えば、厳しい護摩修行を思い浮かべる方も多いかと思いますが、なかなか他宗派の方にとっては縁遠い存在の護摩祈祷。それを目の前でお参りできる貴重な機会が今回のツアーの目的です。ただでさえ暑い夏なのに~さらに火を焚いてご祈祷?!はい!今回のツアーテーマは「ホットな夏にお護摩の炎で厄払い」なのです。残暑に炎の暑さも加わって厄払いも効果が増しそうな気配。 さて、お護摩の祈祷法要を行ってくださるのは真言宗豊山派の明王院の市橋杲潤(いちはしごうじゅん)師。 実は、三田界隈はお寺が沢山ある場所の一つ。お寺が並ぶ一角に明王院はありました。古くは江戸時代に八丁堀にあった大師様とお不動様を当地に移したそうで、「厄除け大師」として江戸の昔から大切に守られてきたのだといいます。他にも本堂には、当時氾濫した川の竜を退治したという伝説と共に、竜頭の骨とされるものがお祀りされ信仰の対象とされてきたのだそうで、文化文政よりも古い時代のものらしいとのことでした。
-

4/15 仏教ひとまわりツアー「死の体験旅行」の報告
仏教ひとまわりツアー
2015-04-18
自分の「死」を疑似体験しながら、 普段は考えない自分の心を見つめる企画「死の体験旅行」が、定員20名、一人の遅刻もなく集合し開催されました。 今回は体は動かず、心とイメージで行うツアーです。 会場は西新宿のビル街にあります浄土真宗本願寺派淨音寺。 お寺に見えない外観ですが、室内はヒノキの香りが広がる温かみのある空間です。 「死の体験旅行」というと中には最近はやりの「入棺体験」のようなものと勘違いされていたかたもいたようで、さぞ驚かれたと思います。 ファシリテーターの浦上さんの落ち着いた通る声が皆の心と脳に深くしみて行き 途中で色々な感情が湧き上がったかたも多かったと思います。 内容は、今後別の場所で受ける方もいらっしゃるので、ここでは詳しく書くことはしませんが、寺ネット・サンガで取り上げるにしては、かなり深い企画ではありました。 最後に淨音寺の高山住職から、 今日の結果は「今」の結果であり変わっていくこともあるというお話をいただき、 人の想い、ということを改めて考えました。 このプログラムは、なごみ庵の庵主 浦上哲也さんが講師として開催しているワークショップです。 今回逃したかたは、こちらからどうそ。 http://www.machitera.net/project/spirit_body/death/
-

仏教ひとまわりツアー 各宗派本山めぐり「總持寺」
仏教ひとまわりツアー
2014-11-05
2014年11月1日(土)、寺ネット・サンガ主催「仏教ひとまわりツアー」が開催されました。「修行僧の毎日」に焦点をあてた全4回ツアー「各宗派本山めぐり」も、いよいよ最終回となりました。今回は横浜市鶴見区にある曹洞宗大本山總持寺です。 はじめに總持寺の本山布教教化部の蔵重宏昭老師から、お寺のご縁起や曹洞宗について、修行の要である「坐禅」についてのお話を伺いました。 修行僧(雲水)の毎日は、坐禅に始まり、坐禅に終わります。日々のスケジュールは「清規(しんぎ)」と呼ばれ、新米のお坊さんも、えらいお坊さんも同じ日程で生活しているそうです。 ※修行僧のスケジュールについては、前回の「坊コン」にて正山寺ご住職、前田宥全さんの「禅の生活」でお話を伺っています→http://www.eijuin.jp/News/view/9/508 ○調身・調息・調心(ちょうしん・ちょうそく・ちょうしん)ー生活をととのえるー 「調身・調息・調心」=身をととのえ、呼吸をととのえ、心をととのえることの大切さについてお話がありました。 人間の身でありながら仏であり続けられたお方、お釈迦さまは坐禅によってお悟りを開かれました。曹洞宗では「私たちも及ばずながらお釈迦さまの真似していきましょう」という心で、坐禅の修行を大切にしているそうです。 世の中は「縁起」しており、お互いがお互いにかかわりあって調和しています。ところが私たちの心の中には「無明(むみょう)」と呼ばれる根本的な煩悩があり、油断するとわがまま心が出てきます。「私が、私が」という心を抑えて、調和する生活を送るために、日常生活をととのえることは大切なことです。 日々の繰り返しの中で、人は怠け心が出てきます。お互いに注意し合い、励まし合って、生活をととのえる中心となるのが坐禅です。 ○基本姿勢は「精進(しょうじん)」=精にして雑ならず、進んで退かず 「精進」=精にして雑ならず、進んで退かずとは、「積極的な気持ちで、ひとつひとつのことを丁寧にやっていくこと」です。作法が細かく決まっているのは、ひとつひとつのことを丁寧に行なう「精進」の心を大切にしているからだそうです。 また、「喫茶喫飯(きっさきっぱん)」という言葉についてもお話がありました。「喫茶喫飯」の言葉には、食事の時は食事のことだけをする、というシンプルな教えが含まれています。日々、その時その時のことをきちんと丁寧にやっていくことで、いざという時に行動に移すことができます。丁寧に物事をこなすことで、人に対しても、きめこまやかな対応ができるようになります。 「丁寧に、その時その時をきちっとやっていくことが、本物の思いやり(=慈悲)につながるのではないでしょうか」と、お坊さんからのお話がありました。
-

仏教ひとまわりツアー 各宗派本山めぐり「増上寺」
仏教ひとまわりツアー
2014-09-01
2014年8月30日(土)、寺ネット・サンガ主催「仏教ひとまわりツアー」が開催されました。 各宗派の大本山をめぐりながら、「修行僧の毎日」に焦点をあてた「仏教ひとまわりツアー」。第3回目のお寺は、東京タワーの近く、徳川家の菩提寺としても知られる浄土宗大本山「増上寺」です。 当日は40名以上の参加者が集まり、賑やかなツアーとなりました。 増上寺のお坊さんから、境内の案内を兼ねて「修行僧の毎日」についてお話を伺いました。 ○浄土宗とは 鎌倉時代、政権争いの他、飢饉や疫病などの天災によって、人々は不安の中暮らしていました。僧侶たちは権力者と結びつき、貧しい庶民は救われることなく、すがるものもありませんでした。 比叡山では「智恵第一の法然房」と称されるほど、勉強熱心であった法然上人は、皆が平等に救われる道を求めます。法然上人は『一切経』の中から、阿弥陀様の御本願四十八願のうち、第十八番目にすべての人々が平等に救われる道を見いだしました。 法然上人のお言葉に、「智者(ちしゃ)のふるまいをせずしてただ一向に念仏すべし」とあるそうです。自身の至らなさを自覚(愚者の自覚)し、「こんな私ですが、どうぞお救い下さい」とお念仏を一心にお称えして阿弥陀様に救いとって頂き、西方極楽浄土に生まれることを願います。 浄土宗のお坊さんの修行の基本は、一心に「南無阿弥陀仏」とお称えすることだそうです。 お念仏の「南無」の部分は「帰依します」という意味で、お坊さんたちは節をつけて、ひたすらお称えします。 本日も移動中の廊下では、修行しているお坊さんのお念仏の声が、絶え間なく聞こえていました。
-

仏教ひとまわりツアー 各宗派本山めぐり「川崎大師」
仏教ひとまわりツアー
2014-07-01
2014年6月28日(土)梅雨空の中、寺ネット・サンガ主催「仏教ひとまわりツアー」が開催されました。 各宗派の大本山をめぐりながら、「修行僧の毎日」に焦点をあてたツアーです。 第2回目は、川崎の真言宗大本山「川崎大師平間寺」です。 真言宗智山派大本山「金剛山金乗院平間寺」は、広く「川崎大師」の名称で親しまれているお寺です。 お正月には約300万人の人が参拝に訪れるという「川崎大師」。 お護摩修行には、ツアー参加者の他にもたくさんの方々が参拝に訪れていました。 お護摩の修行時間は、川崎大師のホームページでご確認頂けます。 ○お護摩の修行 護摩壇の周囲に、香華や五穀、お供物をお供えし、導師が中央の炉の中に護摩木(ごまぎ)を焚いて、ご本尊・厄除弘法大師さまのご供養にはじまる秘法です。 燃え上がる炎に不動明王の剣を象ったお護摩札をかざし、煩悩を焼き、浄化することで家内安全、災厄消除、所願成就を祈願します。 その際、お大師さまのご宝号である「南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)」とお唱えします。 「仏教ひとまわりツアー」参加者たちは、迫力あるお護摩の修行に圧倒されながら、ご本尊の弘法大師空海上人の御尊像に手を合わせました。


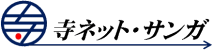


寺ネット・サンガのイベント
「坊コン」
オフィス街でお坊さんとコン談!コン親!コンパ!急な参加も歓迎!定番人気の仏教入門イベントです。
「仏教ひとまわりツアー」
お坊さんたちと一緒に仏教ワクワク体験イベント!宗派宗教を超えて、次はいずこへひとまわり?
「その他の特別イベント」
番外編の特別イベントです。楽しんでいただけたかな?またの機会をお楽しみに!